はじめに
心理現象・心理効果から心理学を逆引きして表示します。
徐々に増やしていきます。(継続編集中)
ページの横断検索は、以下の検索ウィンドウからどうぞ。
通常の心理学用語集はこちら。
心理学のメタファー集はこちら。
認知
| 分類 | 概要 | 用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 感覚・反応・反射 | 繰り返される刺激には慣れや飽きが生じる | 馴化と脱馴化 | |
| 感覚・反応・睡眠 | 揺れや音楽などの刺激があると他の刺激も気にならなくなる(眠くなる) ヒツジを数えることもその応用 | 馴化と脱馴化 | |
| 学習・反応・消去 | 同じ言葉を繰り返すと意味づけが薄れる | ミルク・エクササイズ | |
| 学習・消去・言語 | 思考(雑念)をラベリングすると意味づけが薄れる | ラベリング | マインドフルネス |
| 学習・消去・言語 | 同じ言葉を伝え返されると意味づけが薄れる | 伝え返し | 来談者中心療法 |
| 学習・消去・ | 幼少期などの短期間の経験(学習)が、長期間に渡って強い影響を及ぼす 三つ子の魂百まで | 刷り込み(刻印づけ) | |
| 学習・消去・感情 | 不安・恐怖が強い段階で暴露を中止すると、かえって不安・恐怖が強化されてしまう | 暴露療法(エクスポージャー法) | レスポンデント条件づけ・古典的条件づけ 消去(抑制) |
| 遺伝・生存・適応 | 個体ではなく環境が選択する | 自然選択説(自然淘汰説) | 外在化 |
| 遺伝・生存・適応 | 狂気と創造性は紙一重 | 自然選択説(自然淘汰説) 突然変異 | 外在化 |
| 学習・消去・記憶 | 記憶は完全には消去できない | 忘却曲線 | 節約法・再学習法 |
| 学習・般化・適応 | 一を聞いて十を知る | オペラント条件づけ・道具的条件づけ 汎化 | |
| 学習・強化・動機 | できるだけ早く強化すると効率的 | オペラント条件づけ・道具的条件づけ 即時強化 | |
| 学習・強化・同期 | 遅くなっても報酬を得られる経験をさせる 何度も約束を破られると我慢しても無駄だと学習する | 満足遅延耐性 時間割引率(時間選好率) | 自制心(セルフコントロール能力) 意志力(ウィルパワー) |
| 学習・結合・反射 | 一定の間隔を置いてから対提示すると効率的 | レスポンデント条件づけ・古典的条件づけ 対提示(対呈示) | |
| 学習・結合・感情 | 職場のストレスで上司の顔や声まで憎らしくなる 家庭のストレスでパートナーや子供の顔や声まで憎らしくなる | レスポンデント条件づけ・古典的条件づけ 対提示(対呈示) | 外在化 |
| 学習・結合・感情 | ストレスが多いと自分の呼吸や心臓の鼓動までストレスになる(過呼吸・パニック発作) | レスポンデント条件づけ・古典的条件づけ 対提示(対呈示) | マインドフルネス |
| 学習・弱化・動機 | 逃げ場がなく、何をしても否定されると無気力になる | 学習性無力感(学習性無気力) | 外在化 |
| 学習・結合・感覚 | 外受容感覚ではなく内受容感覚への条件づけで不安などが増大する パニック発作、過呼吸、嘔吐などに至る | レスポンデント条件づけ・古典的条件づけ 内部感覚条件づけ | マインドフルネス |
| 本能・回避・感覚 | トラウマ(心的外傷)を受けると、自分の感情を認識したり、表現したりする能力を失う | 失感情症(アレキシサイミア) | マインドフルネス |
| 学習・愛着・感覚 | 幼少期に形成される基本となる認識パターンは、大人になっても維持される | 愛着(アタッチメント) | |
| 学習・愛着・感覚 | 安定した愛着があれば、そこから世界に飛び出していくことができる | 愛着(アタッチメント) 安全基地 | |
| 学習・愛着・感覚 | 愛着の対象は親であればいいが、親以外でも可能 | 愛着(アタッチメント) | |
| 学習・自己・感覚 | 他者の心の状態(気持ち、信念など)を推測する働きがある | 心の理論 | サリーとアンの課題(誤信念課題) |
| 学習・自己・認知 | 認知についての認知 自己の認知活動そのものを客観的に認知すること 認知していることそのものを認知すること | メタ認知 | |
| 学習・発達・思考 | 思考、雑念 | 内言 | |
| 学習・発達・思考 | 独り言 | 自己中心的言語(自己中心語) | |
| 学習・発達・思考 | 無生物や植物などにも意思や感情があるかのように考える傾向 | アニミズム | |
| 学習・発達・思考 | 過去の経験をもとに構造化された認知的な枠組み 周囲の世界を把握するための認知的な枠組み | スキーマ シェマ(スキーマ) | |
| 学習・問題・思考 | 時間をかけずに経験的に問題解決を行うための手続き・思考法 | ヒューリスティックス(ヒューリスティック) | |
| 認知・問題・思考 | 現在の状態(As Is)と目標の状態(To Be)を比較して、その差(ギャップ)を小さくするように問題解決を行う手続き・思考法 | 手段目標分析 | |
| 認知・問題・思考 | 最終的な目標より手前の目標を設定して問題解決を行う手続き・思考法 | 下位目標分析 | |
| 認知・問題・思考 | 先入観、固定観念、レッテル | ステレオタイプ 代表性ヒューリスティックス(代表性ヒューリスティック) | ジェンダー |
| 認知・社会・思考 | 事前に知っている確率を無視して、後から出てくる確率にだけ注目してしまう | 事前確率の無視(基準率の無視)バイアス | 代表性ヒューリスティックス(代表性ヒューリスティック) |
| 認知・問題・思考 | ある情報(アンカー)を与えられたら、それに思考が引っ張られてしまう | アンカリング(アンカリング効果) 係留と調整ヒューリスティックス(係留と調整ヒューリスティック) | |
| 認知・問題・思考 | 正常なときの経験に引っ張られてしまう | 正常性バイアス | シミュレーション・ヒューリスティックス(シミュレーション・ヒューリスティック) |
| 認知・仮説・思考 | 自分にとって都合のいい情報ばかりを無意識に集め、間違いだと立証する情報は目に入らなくなる | 確証バイアス | ウェイソン選択課題(4枚カード問題) |
| 認知・社会・思考 | どこに焦点を当てて表現するかによって、与える印象が変わる | フレーミング効果 | |
| 認知・社会・思考 | 報酬よりも損失のほうを大きく評価する心理的傾向 | 損失回避バイアス(損失回避の法則) | |
| 認知・問題・思考 | ものの機能(用途)に固着(固執)するあまり、そのほかの機能(用途)に気づかなくなる 発想が固定観念や先入観にとらわれてしまい、別の発想が浮かばなくなる 収束的思考から発散的思考への切り替えが困難 | 機能的固着(バイアス) | ロウソク問題 |
| 認知・問題・思考 | 問題から離れて温める時間をとることで、まったく新しい創造的な問題解決(アイデア)を着想しやすくなる 真面目に考えすぎても、煮詰まってしまう 収束的思考から発散的思考への切り替え | 孵化効果 | 安いネックレス問題 マインドワンダリング |
| 認知・原因・思考 | 他人に指示(命令)されて行動した人に対しても、その人が本来やりたかったからだと考えてしまう | 対応バイアス(基本的帰属錯誤) | 帰属バイアス(帰属エラー) 公正世界仮説(公正世界信念) |
| 認知・原因・思考 | 他人には厳しく、自分には甘く | 行為者-観察者バイアス | 帰属バイアス(帰属エラー) |
| 認知・原因・思考 | 成功は自分のおかげ、失敗は周りのせい | 自己奉仕バイアス(セルフ・サービング・バイアス) | 帰属バイアス(帰属エラー) |
| 認知・原因・思考 | 悪い人には悪いことが起こり、良い人には良いことが起こる 「因果応報」 「自業自得」 「自己責任論」 | 公正世界仮説(公正世界信念) | 対応バイアス(基本的帰属錯誤) |
| 認知・問題・思考 | 先入観や固定観念などにとらわれない、内省的で、偏りのない思考 物事を鵜呑みにせずに、本質を捉える | 批判的思考(クリティカル・シンキング) | |
| 認知・自己・思考 | 自分はできるという可能性を確信できる感覚 「自分はできると期待できる感覚」 「自分はきっとできると思えること」 | 自己効力感(セルフ・エフィカシー) | |
| 認知・自己・思考 | 「自分は価値があると肯定できる感覚」 「自分は自分でいいと思えること」 | 自己肯定感(自尊心・自尊感情) | |
| 認知・自己・思考 | 他人の不幸や失敗を喜ぶ 「他人の不幸は蜜の味」 「他人の不幸で今日も飯がうまい」 「メシウマ」 TwitterなどのSNSで、特定個人を不特定多数の人間が寄ってたかって誹謗中傷する(ネットリンチ) | シャーデンフロイデ | |
| 性格・気質・類型 | 肥満型(太った人)は社交的、融通が効く 細長型(細身型・やせ型)は非社交的、敏感かつ鈍感 闘士型(筋骨型・筋肉型)は几帳面、融通が効かない | クレッチマーの類型論(体格タイプ論) | |
| 性格・気質・類型 | 肥満型は社交的、生活を楽しむ やせ型は非社交的、過敏 筋肉型は活動的、自己主張 | シェルドンの性格類型論(体格タイプ論) | |
| 性格・人格・特性 | 性格・人格の特性は、主に5つの特性に分けられる 神経症傾向、外向性、開放性、調和性、誠実性 | ビッグファイブ理論(特性5因子モデル) | |
| 認知・性格・思考 | 楽観主義(ポジティブ)になる脳の機能 悲観主義(ネガティブ)になる脳の機能 | サニーブレイン(楽観脳)とレイニーブレイン(悲観脳) | |
| 認知・発達・思考 | 「りんご」と聞いて、りんごを思い出す おままごと(ごっこ遊び) | 象徴機能(シンボル機能) | 表象と象徴(シンボル) |
| 単純接触効果 | |||
| 吊り橋効果 | |||
| 返報性の原理 |
行動
| 分類 | 概要 | 用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 遺伝・生存・反射 | 刺激に対して頭や目を向けようとする | 定位反応(定位反射) | 選好注視法(PL法) |
| 遺伝・生存・反射 | 予想外のことに驚く | 期待背反法(期待違反法) | |
| 学習・結合・反射 | 反射的行動(条件反射)を学習する 反射的行動(条件反射)は二次条件づけが可能 | レスポンデント条件づけ・古典的条件づけ 対提示(対呈示)と条件づけ | |
| 学習・強化・行動 | 自発的行動を学習する(試行錯誤) | オペラント条件づけ・道具的条件づけ 強化と弱化 | 試行錯誤説 |
| 学習・強化・行動 | 自発的行動は二次的強化が可能 報酬はトークン(引換券)であっても行動を促進する | トークン・エコノミー法 | オペラント条件づけ・道具的条件づけ |
| 学習・強化・行動 | 目標となる行動をスモールステップに分けて段階的に習得する | シェーピング法 反応形成(シェーピング) | オペラント条件づけ・道具的条件づけ |
| 学習・連携・行動 | 不安や恐怖などの条件反射(レスポンデント)の起こる環境に向かうきっかけ・手がかりとして、褒めるなどの自発的行動(オペラント)の強化を用いる | シェーピング法 から 系統的脱感作法 | オペラント条件づけ・道具的条件づけ から レスポンデント条件づけ・古典的条件づけ |
| 学習・連携・行動 | 追いかけるなどの自発的行動(オペラント)のきっかけ・手がかりとして、くわえるなどの無条件反射(レスポンデント)を用いる | 自動反応形成(オートシェーピング) | レスポンデント条件づけ・古典的条件づけ から オペラント条件づけ・道具的条件づけ |
| 学習・強化・行動 | 罰は行動を抑制するだけでなく逃避・回避行動を促進することもある | 強化と弱化 | オペラント条件づけ・道具的条件づけ |
| 学習・強化・行動 | たまのご褒美の方がやる気が出る ご褒美は徐々に減らした方が長続きする | 部分強化効果(間欠強化効果) | オペラント条件づけ・道具的条件づけ |
| 学習・強化・行動 | 給料日などの報酬の後にやる気がなくなる | 強化スケジュール 強化後休止(強化後反応休止) | オペラント条件づけ・道具的条件づけ |
| 動機・強化・行動 | 過程(プロセス)を楽しむため、行動すること自体がご褒美 自分が決めた目標に対して、時間を忘れて夢中になる 「好きこそ物の上手なれ」 | 内発的動機づけ | |
| 動機・強化・行動 | 結果(ゴール)を求めるため、ご褒美は行動のあとになる 環境や他者が決めた目標に対して、早く終わらせることばかり考える | 外発的動機づけ | |
| 動機・強化・行動 | 報酬などの外発的動機づけ(誘因)によって、すでにあった内発的動機づけが低下する 楽しんでやっていたことが、報酬(ご褒美)を得る仕事になることで、やる気(モチベーション)が下がってしまう | アンダーマイニング効果 | 内発的動機づけと外発的動機づけ |
| 動機・強化・行動 | 言語的な報酬などの外発的動機づけ(誘因)によって、内発的動機づけが高まる 内発的動機づけを高めるには、お金などの物理的な報酬ではなく、褒めるなど言語的な報酬 | エンハンシング効果 | 内発的動機づけと外発的動機づけ |
| 動機・強化・行動 | 内部から行動を引き起こす要因 | 動因(欲求) | 内発的動機づけ |
| 動機・強化・行動 | 外部から行動を引き起こす要因 | 誘因 | 外発的動機づけ |
| 動機・強化・行動 | 低次な欲求(動因)がある程度満たされることで、より高次な欲求(動因)が現れる | マズローの欲求5段階説(欲求階層説・自己実現理論) | 動因(欲求) 一次的欲求と二次的欲求 欠乏欲求と成長欲求(存在欲求) |
| 動機・強化・行動 | 欠乏欲求は強く、成長欲求は弱い 欠乏欲求は続かないが、成長欲求は継続する 欠乏欲求は環境に振り回されるが、成長欲求は自由 | 欠乏欲求と成長欲求(存在欲求) | 動因(欲求) マズローの欲求5段階説(欲求階層説・自己実現理論) |
| 防衛・適応・行動 | 欲求が阻害されると、攻撃、逃避、防衛などが起こる | 欲求不満(フラストレーション) 適応機制 | 適応機制 防衛機制 |
| 防衛・適応・行動 | 欲求不満(フラストレーション)や葛藤から自己を守るための心理メカニズム | 防衛機制 | 適応機制 |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい体験や現実を、受け入れようとしない 依存症や死に至る病の患者で、よく見られる | 否認(防衛機制) | 防衛機制 キューブラー・ロスの死の受容過程(5段階モデル) 否認の病 |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい自分の感情や欲求を、他人のものであるかのように押し付ける(妄想の一種) | 投影・投射(防衛機制) | 防衛機制 境界性パーソナリティ障害(BPD) 統合失調症 |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい感情や欲求から、幼少期の精神状態(発達段階)に逆戻りする 「子ども返り」や「赤ちゃん返り」と言われる現象 | 退行(防衛機制) | 防衛機制 |
| 防衛・適応・行動 | 他人の属性(感情、価値観など)を自分のものにする | 取り入れ・摂取(防衛機制) | 防衛機制 |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい感情や欲求を、意識から無意識の世界に押しやる | 抑圧(防衛機制) | 防衛機制 |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい感情や欲求から、本心とは反対に振る舞う 「慇懃無礼」、「馬鹿丁寧」 | 反動形成(防衛機制) | 防衛機制 強迫性障害(OCD) |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい感情や感覚を、思考や行為(行動)から切り離す(麻痺する) | 隔離・分離(防衛機制) | 防衛機制 強迫性障害(OCD) |
| 防衛・適応・行動 | 過去の思考・行為によって生じる感情(罪悪感、恥など)を、反対の思考・行為で打ち消す | 打ち消し・取り消し(防衛機制) | 防衛機制 強迫性障害(OCD) |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい体験や記憶を、正常な意識から切り離す | 解離(防衛機制) | 防衛機制 解離性障害 PTSD(心的外傷後ストレス障害) 境界性パーソナリティ障害(BPD) |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい感情や欲求を、別の対象に向ける 「八つ当たり」 | 置き換え(防衛機制) | 防衛機制 |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい感情や欲求を、もっともらしい理由をつけて自分を納得させる 「言い訳」、「すっぱい葡萄」 | 合理化(防衛機制) | 防衛機制 |
| 防衛・適応・行動 | 相手に向けている感情(怒りなど)を、自分自身に向ける | 自己への向き換え・自虐(防衛機制) | 防衛機制 |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい感情や欲求と、反対の感情・欲求に変わる | 転倒・逆転(防衛機制) | 防衛機制 |
| 防衛・適応・行動 | 反社会的行動を、学問や芸術、スポーツなどの社会的行動に転換する | 昇華(防衛機制) | 防衛機制 |
| 防衛・適応・行動 | 受け入れがたい感情や欲求から、他人に自分を重ね合わせ、自己評価を高める | 同一視・同一化(防衛機制) | 防衛機制 |
| 防衛・適応・行動 | 避けられない死の悲しみを、否認・怒り・取引・抑うつ・受容の5段階を経て受容していく | キューブラー・ロスの死の受容過程(悲しみの5段階モデル) | 否認(防衛機制) |
| 防衛・適応・行動 | 欲求を満たす目標が複数あるときに、迷ってしまって行動を起こせない | 葛藤(コンフリクト) | |
| 学習・間接・行動 | 刺激が消失してからしばらく時間が経っても、消失した刺激に対して反応できる | 遅延反応 | |
| 自制・時間・行動 | 目の前の報酬には手が伸びてしまうが、すぐ手に入らない報酬は比較的我慢できる はじめに立てたルールを守り続けられる環境を整える 「形から入る」 | 時間割引率(時間選好率) 双曲割引 現在バイアス(現在志向バイアス) 時間的非整合性(動学的不整合性) | 環境調整 |
| 自制・時間・行動 | 遠い将来なら待てるが、近い将来なら待てない 将来の大きな利益より、目の前の小さな利益を追ってしまう 現在の自分が未来の自分を売り渡す 先延ばし(後回し) 明日やろうは馬鹿野郎 | 時間割引率(時間選好率) 双曲割引 現在バイアス(現在志向バイアス) | |
| 自制・時間・行動 | 計画時は自制的だが、実行時は衝動的になってしまう | 時間的非整合性(動学的不整合性) | |
| 自制・時間・行動 | 将来の報酬は簡単に受け渡しても、将来の損失は簡単には受け入れようとはしない | 符号効果 | |
| 自制・時間・行動 | 「得したい」と報酬的に考えると先延ばしするが、「損したくない」と損失的に考えると先延ばししにくい | 符号効果 | |
| 学習・回避・行動 | 不安・恐怖の生じる事象に直面すると、不安・恐怖に慣れる | 暴露(エクスポージャー) | |
| 自制・回避・行動 | 安全を確保しようとして回避する行動は、短期的には不安を解消することができるが、長期的には不安が増大して逆効果となる | 安全行動(安全確保行動) | |
| 自制・回避・行動 | 現実の体験を回避しすぎると、不安や悩みが悪化してしまいやすい | 心理的柔軟性 体験の回避 | ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー) |
| 自制・回避・行動 | 思考にとらわれすぎると、現実が見えなくなってしまいやすい | 心理的柔軟性 認知的フュージョン | ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー) |
| 自制・回避・行動 | 過去や未来にいすぎると、今を生きている実感が得られにくい | 心理的柔軟性 今、この瞬間 | ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー) |
| 自制・回避・行動 | 自分に執着しすぎると、意識が外に向かいにくい | 心理的柔軟性 文脈としての自己(視点取得) | ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー) |
| 自制・回避・行動 | 価値から離れすぎると、生きている意味を見失いやすい | 心理的柔軟性 価値 | ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー) |
| 自制・回避・行動 | 行動が欠如していたり、衝動的だったりすると、価値に向かう行動につながりにくい | 心理的柔軟性 コミットされた行為 | ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー) |
身体
| 分類 | 概要 | 用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 本能・防衛・反応 | ある程度の危険であれば闘争・逃走しようと可動化するが、生命の危機に瀕すると凍りついて不動化する | ポリヴェーガル理論 闘争・逃走反応 凍結反応・凍りつき反応 | マインドフルネス |
| 自律・調節・反応 | 自律神経系(腹側迷走神経複合体)が心臓の心拍数の高止まりを抑えている | ポリヴェーガル理論 ヴェーガル・ブレーキ | |
| 自律・調節・反応 | 呼吸は心臓の心拍変動と同期している 息を吸うと心拍が早くなり、息を吐くと心拍が遅くなる | ポリヴェーガル理論 呼吸性洞性不整脈(RSA) | 呼吸法 マインドフルネス |
| 本能・回避・感覚 | 心理的な問題が身体症状に表現される | 心身症 | |
| 本能・自己・感覚 | 五感以外の身体感覚が自己感覚を形成する | 内受容感覚(身体感覚) 第六の感覚(第六感) | |
| 本能・自己・感覚 | 胸に手を当てる(胸に手を置く) | 内受容感覚(身体感覚) | |
| 本能・自己・感覚 | 腹落ちする | 内受容感覚(身体感覚) | |
| 本能・自己・感覚 | 耳が痛い | 内受容感覚(身体感覚) | |
| 本能・自己・感覚 | 目は口ほどに物を言う | 内受容感覚(身体感覚) | |
| 本能・防衛・反応 | 過度な防衛反応を起こさないためには、自律神経系を最適覚醒状態に維持する必要がある | 耐性領域(耐性の窓) | |
| 自律・防衛・反応 | 生命維持は自律的に行われている | 自律神経系 | |
| 自律・防衛・反応 | ストレスなどの外部環境に対して、内部環境を一定に維持しようとする | ホメオスタシス(恒常性) | |
| 自律・防衛・感覚 | 情動はホメオスタシス調節の一部である | 防衛反応 | |
| 自律・防衛・反応 | ストレスなどの外部環境に対して、生体を変動・調節することで、内部環境を安定させようとする | アロスタシス(動的適応能) | |
| 遺伝・自己・反応 | 遺伝子(DNA)は不変ではなく、遺伝子(DNA)が原因なのか、環境が原因なのかを区別することは困難 | エピジェネティクス | |
マーケティング
| 分類 | 概要 | 用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 学習・結合・感情 | 好感度の交換 | 対提示(対呈示)と条件づけ | レスポンデント条件づけ・古典的条件づけ |
| 学習・強化・行動 | ポイントカードやスタンプカードなどのトークン(引換券)を用いて顧客をリピーターに育成する | トークン・エコノミー法 | オペラント条件づけ・道具的条件づけ |
| 学習・強化・行動 | トライアルやお試しなどのスモールステップに分けて申し込みや購入につなげること | シェーピング法 反応形成(シェーピング) | オペラント条件づけ・道具的条件づけ |
| 学習・強化・行動 | 毎回報酬を得るより、ときどき報酬を得た方が条件づけは持続する(ギャンブル依存、ゲーム依存、射幸心) | 部分強化効果(間欠強化効果) | オペラント条件づけ・道具的条件づけ |
| 学習・強化・行動 | ゲームなどの継続(ログイン)ボーナス | 強化スケジュール 固定間隔スケジュール(FI) | オペラント条件づけ・道具的条件づけ |
| 自制・時間・行動 | 今だけお得なキャンペーンに人は食いつく 使ったその日の効果を訴求する | 現在バイアス(現在志向バイアス) | |
| 自制・時間・行動 | いずれ必ず購入する商品などは、今を逃すと損すると訴求する | 符号効果 | |
経済
| 分類 | 概要 | 用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 経済・報酬・信用 | 価値の低い硬貨・紙幣であっても、強化によって信用形成することができる | トークン・エコノミー法 トークン・エコノミー(トークン経済) | |
| 経済・報酬・自制 | 経済的な余裕が自制心(セルフコントロール能力)を生み出す | 時間割引率(時間選好率) マシュマロ実験(マシュマロ・テスト) | |
| 経済・報酬・自制 | 給与天引きや自動的な貯蓄・積立で、衝動的な消費・浪費からお金を退避させる | 時間割引率(時間選好率) 双曲割引 現在バイアス(現在志向バイアス) 時間的非整合性(動学的不整合性) | 積立 |
組織
| 分類 | 概要 | 用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 学習・観察・動機 | 職場にフレッシュな新人を採用することで、無気力に陥った人材の再活性化を行う | 学習性無力感(学習性無気力) カマス理論 | 観察学習(モデリング) |
| 学習・弱化・動機 | うまくサボった方が意欲が出て貢献できる | 学習性無力感(学習性無気力) | 外在化 |
| 学習・強化・動機 | 心理的安全性があると、コミュニケーションが活発化し、生産性が向上(パフォーマンスが向上)し、イノベーションの創出につながる | 心理的安全性 | 学習性無力感(学習性無気力) |
| 人材・生産・感情 | 最高のチームに最も重要な要素は心理的安全性 | 心理的安全性 | コーチング |
| 自制・時間・行動 | 徐々に計画から逸脱してしまうため、定期的に計画を見直す | 時間的非整合性(動学的不整合性) | |
| 研究・臨床・行動 | 執筆者や学会など審査機関にとって望ましい結果の出た研究・論文ばかり公表されること エビデンスは後年になって誤りとわかることもあるため、エビデンスを人に押し付けないようにする(インフォームド・コンセント) エビデンスを盲信することなく、臨床で確認する(特に心理療法は個体差が大きいため重要) | 出版バイアス | 臨床 |
| 研究・臨床・行動 | 臨床的な実験・経験によって知見が集められること どんな理論も臨床によって初めて確からしさがわかる “Empirical”は”Experiment(実験)”と”Experience(経験)”を組み合わせた造語 | エンピリカル (Empirical) | 臨床 |
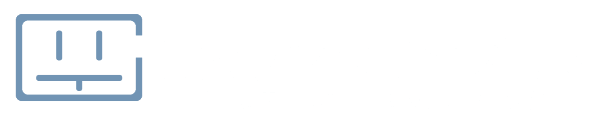
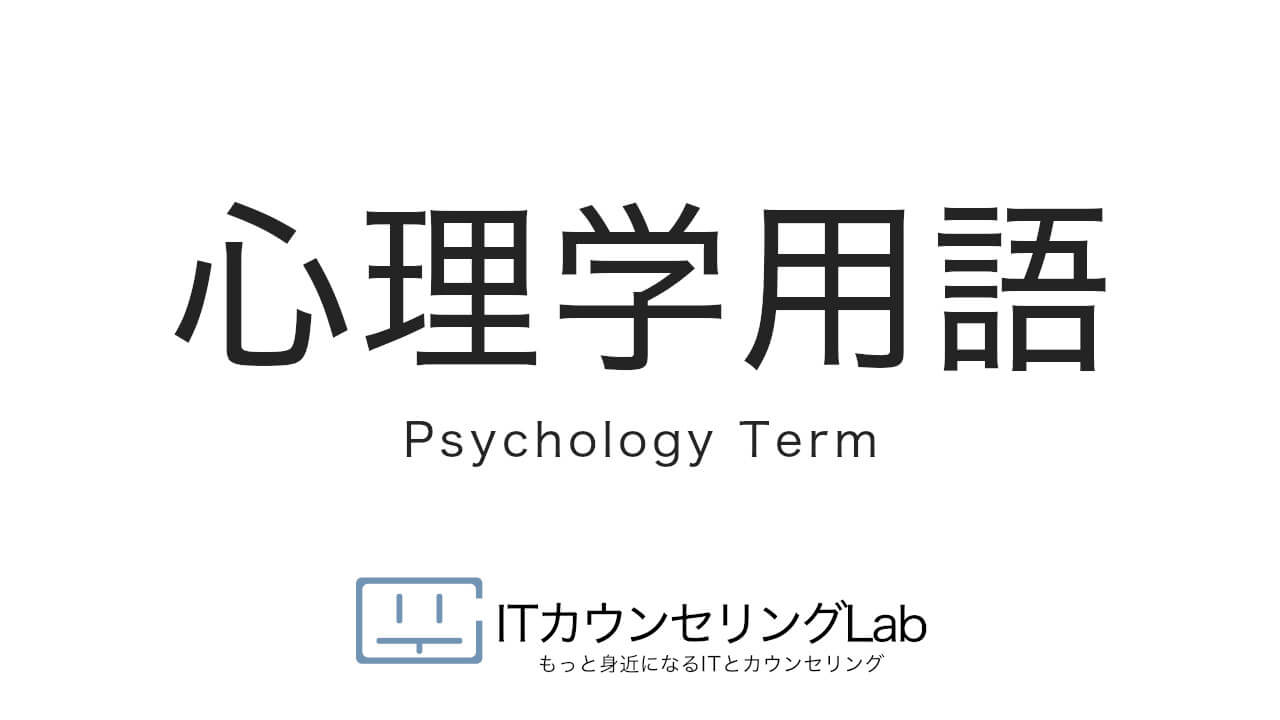
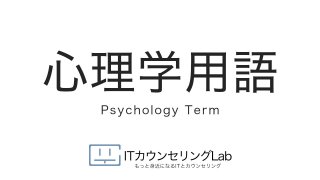
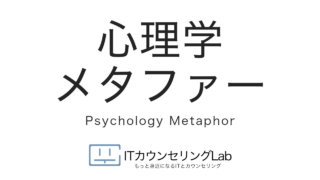
コメント