ホメオスタシス(恒常性)とは
ストレスなどの外部環境に対して、内部環境を一定に維持しようとする生体機能のこと。
生体は酸素、血圧、血糖、体温などの自己調節を行う。
フランスのクロード・ベルナールが提唱し、アメリカのウォルター・B・キャノンが命名した。
「ホメオスターシス」や「ホメオダイナミクス」、「恒常性維持」や「生体恒常性」とも言う。
例えば、気温が上がれば、汗をかいて体温を下げる。昼は暑く夜は冷える砂漠地帯でも生きていける。
例えば、怪我をしても自然治癒力で治る。運動して乳酸がたまっても酸性(pH)は中和される。
このように、生体外や生体内の状態に対するネガティブフィードバック作用(負のフィードバック作用)が働くことで、ホメオスタシス(恒常性)は維持されている。
ヒトのホメオスタシス(恒常性)は大変発達しているため、冬眠する必要もないし、水辺を離れて暮らすこともでき、砂漠や氷雪地帯など地球上の広範囲に適応している。
最近では、ストレスなどの外部環境に適応するために、生体を変動・調節することをアロスタシス(動的適応能)と呼ぶ。
ホメオスタシスと生体システム
ホメオスタシス(恒常性)は、神経系(自律神経系)、内分泌系(ホルモン)、免疫系、細菌叢(腸内細菌)などによって機能している。
例えば、出血で血圧が低下すると、交感神経-副腎髄質系でアドレナリンが分泌され、血管収縮によって血圧を上昇(維持)させたり、肝臓と連携して血液を凝固しやすくなり、唾液分泌が減って喉が乾く。
ストレスやトラウマなどにより、自律神経系のバランスが崩れた状態を自律神経失調症と呼び、ホメオスタシス(恒常性)が維持できない状態である。
ホメオスタシス(恒常性)を維持できないほどの体調不良がある場合は、恒常性を損なう悪循環が生じていることが考えられる。
例えば、冷え性の人の身体は、体温を上げようとするホメオスタシス(恒常性)が働いて、交感神経系が常に優位になってしまう。
交感神経系がずっと働いていると、自律神経が疲れ切ってしまい、反動がきて逆に冷え性が悪化する悪循環に陥る。
以下は、ウォルター・B・キャノンがホメオスタシス(恒常性)について記した著作『からだの知恵』。
以下の図は、ホメオスタシス(恒常性)を命名したウォルター・B・キャノン。

ホメオスタシスと防衛反応
防衛反応とホメオスタシス(恒常性)は相互に関係している。
例えば、交感神経系やアドレナリンの作用によって、防衛反応が引き起こされることも、広義のホメオスタシス(恒常性)だと言える。
逆に、免疫系によって、細菌やウイルスなどに対する防衛反応が絶えず生体内で行われている。
ホメオスタシスと情動
アメリカのアントニオ・ダマシオは、「情動はホメオスタシス調節の一部である」と言っている。
つまり、ヒトは適切に防衛反応などの行動を行うために、情動を必要としているのである。
情動を感じるのは、ホメオスタシス(恒常性)の生理的信号によるものかもしれない。
参考
関連する心理学用語
自律神経失調症
闘争・逃走反応(fight-or-flight response)
新行動主義
S-O-R理論
第三世代の認知行動療法
マインドフルネス
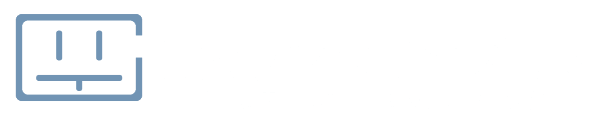
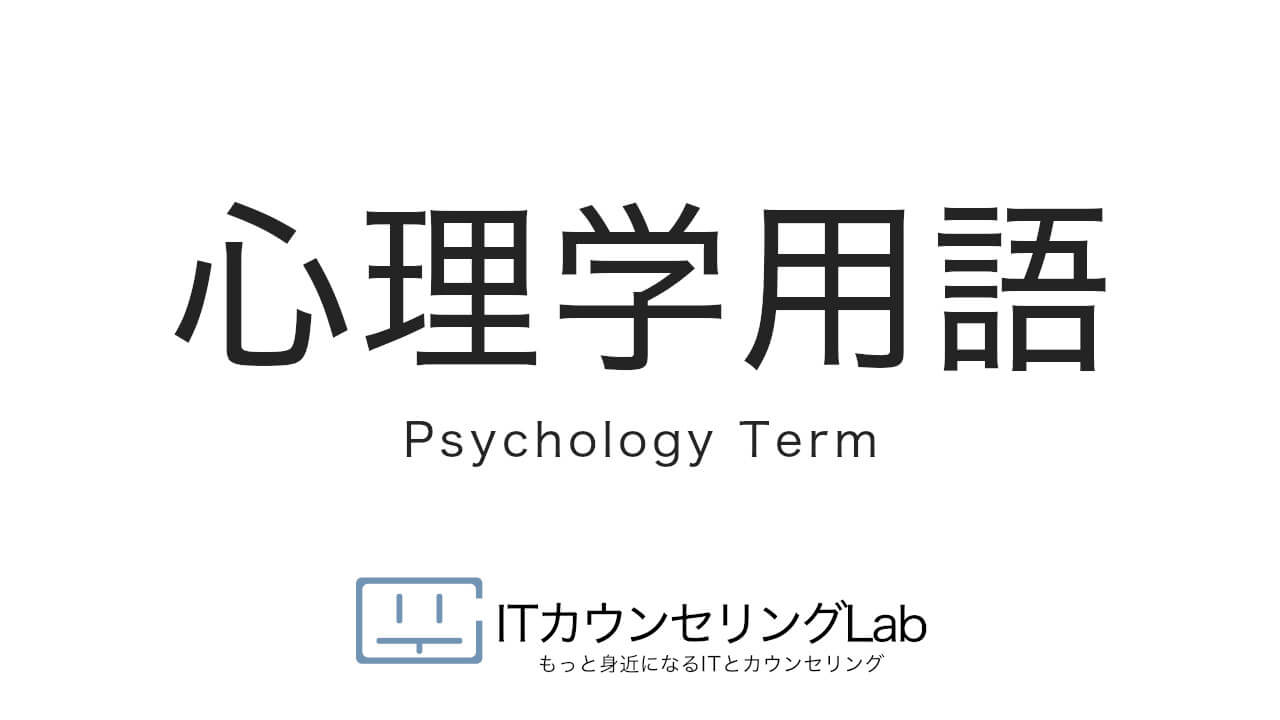
コメント